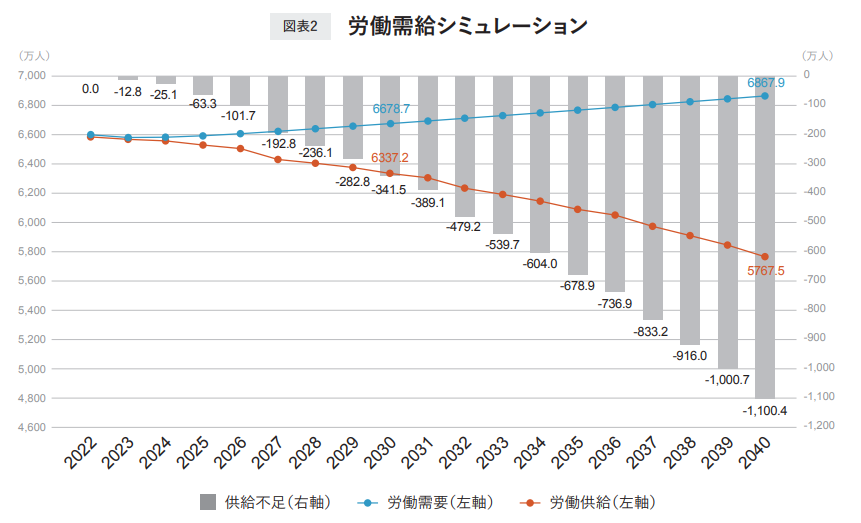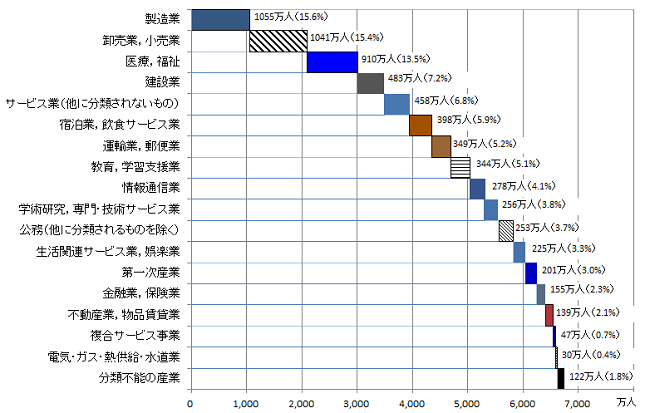日本では35℃を超える日が続き、度々危険な暑さを感じる夏を過ごすようになりました。10年前にはそこまで多い印象がなかったゲリラ豪雨の頻度も明らかに増えるなど、日本でも多くの人が気象の変化をここ数年で急激に体感するようになったのではないでしょうか。
こうした変化には気候変動の影響があると言われています。
実際、2024年の1月から6月までは「最も暑い半年」を私たちは過ごしています。
以下の図の太線で示されるとおり、2024年のすべての月で、世界全体の気温は過去最高となりました。現在のところ、2024年は2023年よりも0.14℃、たった8年前の2016年よりも0.4℃程度暑くなっていると言われています。

2023年2月から2024年2月の間を取ってみると、世界の平均気温は産業革命以前に比べて1.52度上昇したというニュースもありました。上記の図の点線 (2023年) と黒線 (2024 年) を見ても、数ヶ月間 1.5 ℃を超え続けていることが見て取れます。
地球の気候は変わりつつあります。
現状
日本でも脅威を伝え始める動きが活性化
気候変動は生態系や人類社会に甚大な影響を与えると予想されています。その危険性から、昨今では気候変動 (climate change) ではなく気候危機 (climate crisis) という単語もしばしば使われます。
日本はそうした気候変動や気候危機の報道が少ない国だと言われていましたが、状況は変わり始めています。
たとえば今年に入って、気象予報士や気象キャスターの方々による共同声明が出され、気象と気候変動を関連づけた発信に力を入れていくことが宣言されました。保健医療分野でも気候変動対策が必要という提言書が日本医療政策機構からも出てきています。
これから日本でも気候変動がより多く取り上げられ、注意喚起や警告が行われるようになるのではないかと思います。
人は恐怖で立ちすくむ
そうして気候危機に関する認識が広まっていくと、脅威や不安を感じる人も多くなるでしょう。いわゆる気候不安やエコ不安と呼ばれているもので、それは自然な反応です。
特に日本は気候不安を感じる人が相対的にかなり少ない国だったので、もし報道が増えれば、他国に比べてそうした不安を抱える人は増えていくのでは、と思います。
ただ、注意したいのは、人は脅威や不安を感じると、その場で立ちすくむんでしまうこともある、ということです。諦めを感じて何も行動しないことを選んだり、逆にその脅威を否認するような反応をしうる、ということです。
たとえば、迫り来る脅威が大きいことを伝えられると、抵抗する気力をなくし、諦めてしまう人もいます。「どうしようもない」「なんとでもなれ」「仕方がない」という消極的な態度を取ってしまうこともあるでしょう。
認知バイアスの問題もあります。正常バイアスによって、私たちは危機やその予兆を無視したり、過小評価してしまいます。また現状維持バイアスなど、変化という負担を好まない傾向もあります。
危機が起こっているとひとまず認識したとしても、認知的不協和によって「気候変動など起きていない」「気候変動があったとしても対処する必要はない、大丈夫だ」「気候変動対策には別の問題があるからしないほうがよい」といった否認に傾くこともあるでしょう。

2020 年前後にも似たようなことがありました。「コロナウィルスで不安を感じたくない」と思ってしまうせいか、「コロナウィルスなど存在しない」といった問題の否認をしたり、そこからさらに「問題がないのだから、ワクチンという解決策など必要ない」「解決策と言われているワクチンは意味がないし、むしろ危険だ」といった心理を辿ったような発言を見た方も多いのではないかと思います。
先ほどの言葉の中で、コロナウィルスという言葉を気候危機、ワクチンを気候危機緩和策に入れ替えてみてください。「気候危機で不安を感じたくない」➡「気候危機など存在しない」、「危機がないのだから、緩和策という解決策など必要ない」「解決策と言われている各種緩和策は意味がないし、むしろ危険だ」といった発言もしばしば見ることに気づかれるのではないでしょうか。
(ただしワクチンと異なり、緩和策はそれぞれ良し悪しがあるので、意味のない緩和策もあるとは思います。しかし、すべての緩和策に意味がないかというとそんなことはありません。)
人を動かすには希望が必要
『事実はなぜ人の意見を変えられないのか』という書籍の中では、
- 「何もしないほうがよい」というときは、何かをしたときに報いを受けるかもしれないと警告すること、いわば無行動要請と脅威の組み合わせが有効
- 人に変化をしてほしいなら、行動要請と脅威の組み合わせよりも、行動要請とポジティブな結果の組み合わせのほうが変化を導くには有効
だと紹介されています。
この無行動要請に近いメッセージとして、気候変動の文脈だと「気候変動対策については性急に動いてしまうと、経済的に損をしますよ。だからあなたは何もしないで、このままでいるほうが良いのですよ」という記事を時折見ますが、これは人の変化を止めるという上では有効なメッセージですし、そもそも変わりたくないというバイアスがあるため、一部の人は行動しないことを積極的に選んでしまうでしょう。
逆に行動を促したい場合は、行動の結果として起こるポジティブな面を伝えていく必要があります。
だから、もし人に変わってほしいなら、注意や警告「だけ」ではなく、ポジティブなメッセージ「も」用いる必要があるのだろうと思います。
つまり、これから気候危機の脅威に関しての言及やナラティブが増えるなら、一緒に希望についての言及やナラティブも増やしていく必要があり、希望の語り手がもっと多くならなくてはならないのだろうと思います。
気候変動における希望
では気候変動領域において、希望についてどのような活動や知見があるでしょうか。
時に climate hope とも呼ばれる気候変動における希望については、Örebro University の Ojala による2023 年の心理学的側面からのレビューがあります。そこからいくつかの知見を抜き出してみます。
- まず「希望」にも認知的概念としての希望と感情としての希望がある。
- 気候変動の脅威は大したことがないといった、現実を否定するような「偽りの楽観」や「否定に基づく希望」は気候変動への行動や関与と負の相関がある。
- 建設的な希望は気候変動への関与と正の相関がある。
- 希望が行動につながるだけではなく、行動もまた希望につながる(関与することでより希望を感じる)
これまでの研究を見ても、色々なニュアンスがあることが短い論文の中で指摘されていますが、建設的な希望を作ることはポジティブな影響があるようです。その建設的な希望の中には、技術開発や若者の気候変動運動などが挙げられています。
気候変動運動については、最近も希望にフォーカスした #performinghope というキャンペーンが行われていました。こうした活動も有効でしょう。
そしてもう一つ挙げられているのが技術開発です。私自身は技術寄りの人間ということもあり、テクノロジーに期待しています。そしてそのテクノロジーを実用化し広めていくスタートアップは、気候変動対策に異なる種類の希望をもたらしうる存在であり、これまで気候変動に興味をあまり持たなかった人たちが興味を持つための「入口」となりうるのでは、と個人的には信じています。
そして、今後多く求められる「建設的な希望」の語り手として、Climate Tech スタートアップが果たせる役割も大きいのでは、とも思っています。
Climate Tech スタートアップが作る希望
気候変動対策を行う Climate Tech スタートアップが、気候変動への建設的な希望を作っていくうえで果たせる役目はいくつかあるように思います。
(1) 我慢や負担とは違う、「技術による解決」という選択肢を際立てさせられる
まず気候危機という課題に対して『解決策』があることを伝えることが、希望を構成するために重要な要素です。
しかし、解決策である「環境に良いこと」は、我慢や経済的な負担につながる、という認識をしている人が日本では特に多いようです。
2015年の少し古い調査になりますが、「あなたにとって、気候変動対策は、どのようなものですか?」という問いに対して、日本人の回答は「多くの場合、生活の質を脅かすものである」と回答する人が60%と、世界全体の27%に比べて大きくなっています。

多くの人が、気候変動対策は新たな負担や我慢につながる、と感じているのでしょう。実際、いくつかの対策は、私たちに新たな負担や我慢を強いるものがあるのも事実です。
しかしそれ以外の対策もあります。それがテクノロジーです。
テクノロジーが発達すれば、人の負担を少なくしたまま、変化を起こせるかもしれません。あるいは、従来のものよりも良い製品などが出てくる可能性もあります。
実際、これまでの多くのテクノロジーが人類の繁栄をもたらしてきました。農作物や水道、ソフトウェアなど、苦労していたことをより早く便利にすることを実現してきたのがテクノロジーです。
そしてテクノロジーを早く効率よく普及させていく活動として、営利事業があります。市場のインセンティブをうまく使うことで、テクノロジーを用いた製品やサービスを拡大させることができます。
そうしたテクノロジーと市場によって生まれた問題が環境問題でもあるのですが、「だから問題を起こしたテクノロジーや市場を捨てよう」ではなく、「そのテクノロジーや市場によって生まれた問題も、テクノロジーや市場を修正することによって解決しよう」、というのは一つの有効な態度であると思います。そしてそうした認識が広がれば、その解決策に携わる方法が一つ増え、希望が生まれやすくなるのではないでしょうか。
ただ、これは産業界全般の脱炭素活動に言えることです。では Climate Tech スタートアップならではの点は何でしょうか。
まず一つ、幸いにして、日本国内ではスタートアップ全般に注目が集まっているということです。そのスタートアップへの注目の中で、Climate Tech という領域があることや、そこに今解決に挑もうとする人が集まっていることを伝えられれば、我慢や負担とは違う解決策の存在を改めて伝えることができます。
また、希望を作るときには筋道や明確な目標設定なども有効だと言われています。Climate Tech スタートアップが大きくなることで、その進捗を明示的に伝えることもできるでしょう。またそうしたスタートアップが海外でも活躍して、新しい市場を切り開いていることを伝えられれば、それもまた希望になるのではないかと思います。
(2) 雇用を増やし、関係人口と関与時間を増やせる
気候変動の対策に関与する関係者を増やすこと、特に行動を伴っている人を増やすことは、この問題を解決する上でとても大切だと考えています。
関与の方法として、市民活動に関わることも一つの手ですが、もう一つの手として経済活動に労働者として関わることが挙げられます。市民的な関与の機会だけではなく、経済的な関与の機会が広がることで、より多くの人を巻き込むことができます。
ただ、これまで労働者としてできることは、「環境に悪いことをしている企業を避ける」であったり、「本業ではないCSR等で環境に良いことをしている企業に入る」という選択肢でした。しかしこれでは、気休めか、本業の合間に少し関わるようなことしかできないといった限界がありました。
官僚になって環境問題に取り組む、という選択肢もありましたが、それは狭き門ですし、官僚や大企業はえてして異動が発生し、自分のやりたかったことができない可能性がある、というデメリットもあります。
しかしClimate Techスタートアップのように、「本業・専業として環境に対して良いことをやっている企業」が沢山出てくれば、1日8時間を使って気候変動の問題に取り組めます。CSR ではなくCSV (Creating Shared Value) と言われ始めて久しいですが、その気候変動版ということです。
経済活動での関与の優れた点は、多くの人が多くの時間を使える点だと思っています。仕事として関われば、(営利活動に制限されるとはいえ)1日8時間を使えます。また、実際、グリーンな仕事に就いた人の率が高い地域は、循環型経済の好ましい行動を取るとされており(サーベイ論文)、労働環境が個人の信念に与える影響も大きいのではと思います。
2024年3月に発表された3Mのグローバル調査を見てみても、日本人は「気候変動の影響を感じている」と答えた割合はグローバルに比べても高いという結果になっています。つまり認知は高い状態です。
しかし一方で、若年層は「特に意見はない/気にしない」という回答が世界平均より高かったり、カーボンフットプリントの理解度が他国に比べて突出して低いなどの傾向を見ると、「気候変動は認識しているが、あまり理解していない」という状況です。
そうした状況を変えるためにも、気候変動に深く関わる機会としての雇用は有効な機会ではないかと思います。
そうした会社が成長して雇用が生まれると、そこに関わる人がさらに増えます。そうした点で、スタートアップは貢献できるのではないかと思います。
ただ、雇用の数でいえば大企業の方が多いのは間違いありません。
スタートアップならではの利点は、小さなコミュニティから始められる、という点があるように思います。特に人の社会的な行動を変えるには、小さなコミュニティのほうが有効だと言われているからです。
ペンシルバニア大学の Centola が書いた『Change』という本では、社会変化は周辺から生まれることが指摘されています。そして人を変えるには弱い絆ではなく、強い絆が必要だとも。それを生み出す一つの手段が、新しい会社組織であり、スタートアップであるように思います。
もちろん、大企業が変われば大きな変化にもなります。しかし、インフルエンサーのような社会的つながりが多い人は、つながりが多いが故に「動いていない人が大勢いる」状況に置かれてしまうため、変化を受け入れるのが遅いことが同書で指摘されています。おそらく大企業もそうならざるをえないでしょう。周縁にいるスタートアップのような組織が多く立ち上がってくることは、大きな変化を生みうるのではないかと思います。
それに、仮にスタートアップが大企業の事業を脅かせずとも、もし大企業から Climate Tech スタートアップに人材の移動が多く起こったとしたら、労働供給不足にあえぐであろう大企業も大きく変わっていくでしょう。そうした変化を起こす誘導できるのが、スタートアップではないかと思っています。
社会変化を起こすには、すべての人が変わる必要はありません。3.5%や25%という閾値を超えれば一気に変わるとされています。市場の力を使って関与できる人を増やし、その閾値まで持って行くことができる選択肢が、Climate Techスタートアップが作る希望にもなるように思います。
(3) 希望を語る人を増やせる
リーダーによる希望に満ちたメッセージは、フォロワーが希望を抱くのを助けるそうです。
大企業の社長のようなリーダーが語ると(そのご本人がどれだけ本気で考えていようと)、大企業のポジショントークのように見えてしまいがちです。また個人というよりは会社単位で注目が集まりがちです。
一方で、スタートアップは創業者に注目が集まりやすく、またポジショントーク的な部分もあるとはいえ、個人の面がより取り上げられがちです。取り上げられるときにも、明るい未来や希望を語ることが多いという面もあります。
そうした顔が見えるリーダーが沢山出てくることはきっと希望が周りに伝播しやすくなるのではと考えています。実際スタートアップの創業者だけではなく、そこで働く従業員も未来を語ることが多い印象があります。
スタートアップが社会から求められている役目は、新しい挑戦を行い、未来を語ることです。それが事業の成長にもつながりますし、雇用の増加にもつながります。そうしたスタートアップを多くしていくことが、未来や希望を語る人を多くしていくことにつながり、それが実際の希望へとつながっていくのではないかと信じています。
気をつけたいこと
希望のナラティブを作っていくときに、Climate Tech スタートアップは使えます。とはいえ、Climate Tech スタートアップを無碍に称揚すれば良いというものでもないことは付け加えさせてください。
(a) テクノロジー偏重にならないようにする
テクノロジーが全てを解決してくれるわけではありません。極端な技術解決主義(テクノソリューショニズム)は、むしろ社会的な変化を妨げることもあります。
たとえば「(自分ではない誰かが)新しい技術を開発するから大丈夫」という偽の希望をもたらす可能性もあります。また、実現の可能性の薄い技術や科学的発見を過度に希望として見せると、「これが実現すればきっとすべて解決する」という幻想を抱かせてしまい、直近でできることを促せない、ということもあるでしょう。
気候変動のような複雑な問題には、一つですべてを解決する銀の弾丸があるわけではありません。小さな変化の積み重ねや、社会的な変化も必要です。技術開発や事業開発も、本当に沢山の挑戦を促せなければ解決できないでしょう。それを止めてしまわないようなコミュニケーションが重要だろうと思います。
特にテクノロジーにどっぷり浸かってきた人は(私も含めて)社会問題に対してピュア、というかナイーブであることも多く、その点は気をつける必要があるように思います。
(b) 経済の問題だけにはしない
市場の力をうまく使うと、推進力を得ることができるのは上述したとおりです。一方、日本のビジネス環境を見てみると、社会的な面での気候変動の議論が煮詰まらないまま、国際的な要求とトップダウンの判断で「よく分からないが、とにかく脱炭素をする」という状況になった感もあります。
しかし、もともとは公正 (justice/fairness) や倫理の上で出てきたアジェンダであることは、改めて強調していく必要があるように思います。多くのテクノロジーは市場の中で機能しますが、その市場を作るのは政策であり、政策は単に経済合理性だけではなく、社会的な理想や倫理がその基盤にあります。
それにビジネスや経済、産業、経済安全保障などの実務の問題だけで議論をしてしまうと、本来解決したかった公正や、どういう社会であるべきなのか、といった問題にたどり着けません。
ビジネスの実務上でも、ビジネス上での国際的なルールメイキングなどをしていく際には、そうした視点がないと欧米諸国と議論がすれ違うのでは…と思います。
(c) 希望と危機のバランスを加味する
危機と希望を語るときのバランスは難しいというのが実際のところです。
希望を語りすぎると、人は楽観的になり、行動を起こさなくても良いという判断になってしまいます。希望ばかりを語れば良い問い分けではありません。かといって、危機を伝えすぎると恐怖を感じて行動を起こさなくなるかもしれません。ただし、危機を伝えなければ、その技術や事業の意味を伝えられません。そうしたバランスの中でメッセージを伝えていく難しさがあります。
また、希望を伝えるにせよ、相手に変化を促すことには違いありません。そうした変化を促す言説や危機を訴える言説に説教臭さを感じて「意識高い系」「Woke」と揶揄する人も出てくるでしょう。そうした批判に耐えながら事業を進めることは、それなりに胆力を必要とします。
(d) 実現には努力が必要
Climate Tech スタートアップはあくまで希望であり、可能性でしかありません。本当に気候変動問題に影響するには、実現のための大変な努力が必要です。
希望はあくまで希望で、それを叶えるのが本番です。ただ希望があれば良いというわけではなく、その希望の実現に向けた努力には困難が伴うことは伝えていくべきだろうと思います。
そうした難しいことがあっても、スタートアップという社会的存在に課せられた役目は未来と希望を語り、それを叶えることだろうと思いますし、Climate Tech という領域は、これまでの気候変動と環境系とは異なる人たちに入ってきてもらう『入口』としての機能を果たしうるのではないかと思っています。
危機の語り手が増えつつあり、希望の語り手がそこまで多くない今、Climate Tech スタートアップやその関係者が未来と希望を語り、事業を伸ばし、仲間を増やしていくことは、未来への大きな貢献につながるはずです。
まとめ
希望の語り手は Climate Tech スタートアップ以外にも沢山あります。市民活動などからも多くの人が出てくるはずです。
その上で、経済界などの新たなステークホルダーを巻き込み、希望を作る新たな一つの手段として、今の日本には Climate Tech スタートアップをうまく使う、という選択肢が一つあるのでは、と思います。そしてその Climate Tech スタートアップの成長は、気候に関係する人の数の成長につながります。
そうした希望を語る人たちの増加が、日本の社会における気候変動問題に大きく寄与していくことを個人的には願っています。
その他参考資料
そもそもの気候変動に対する懐疑から、各種の対処策に対する懐疑、経済的合理性の懐疑まで、色々はありますが、よくある懐疑論への返答は Skeptical Science の日本語ページなどを参照してください。
また江守先生の以下の記事などもお勧めです。