イノベーションを考えるときには、基礎研究➡応用研究➡開発➡イノベーションといった線形モデル(供給モデル)で考えてしまいがちです。しかしスタートアップ支援の現場にいると、もう少しシステム的なアプローチで理解するほうが良いのではないかと感じます。
たとえば著名なイノベーション政策研究者である Lund University の Charles Edquist などはこの立場を取っているように思います。
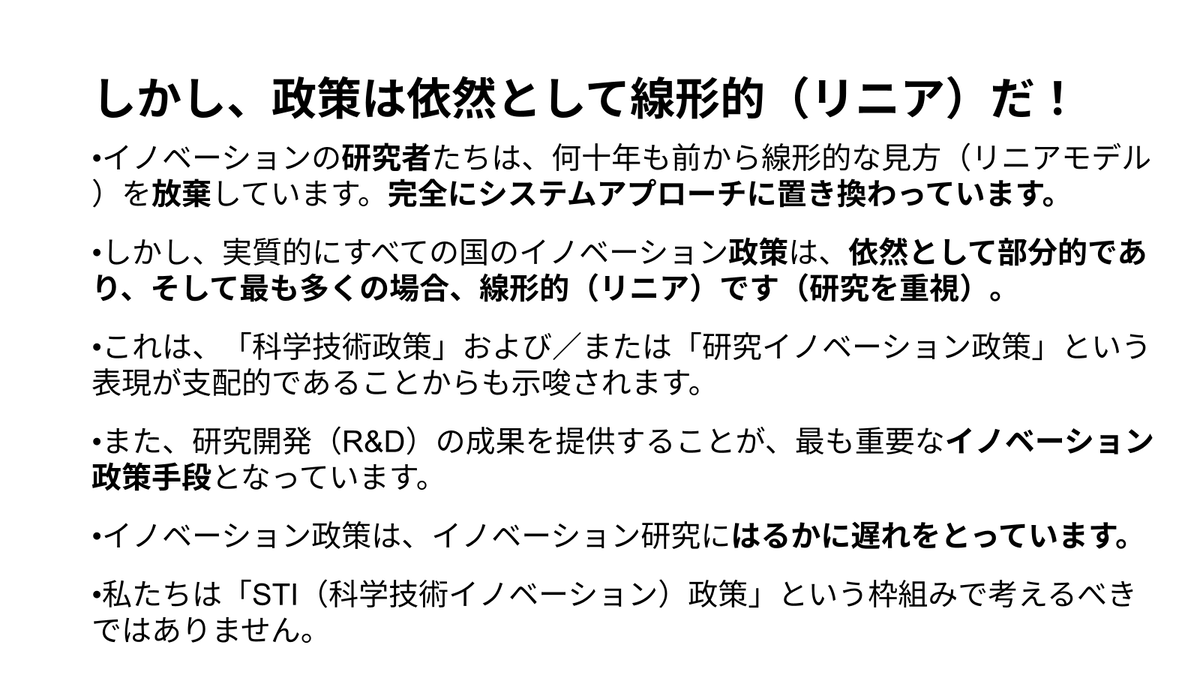
この線形モデルが科学技術イノベーション政策に関わる多くの人の発想の基盤となっているため、イノベーションを起こすときに必要なシステムの全体が十分に考慮されづらいように見えています。全体像の例としては、以下のようなものがあります。
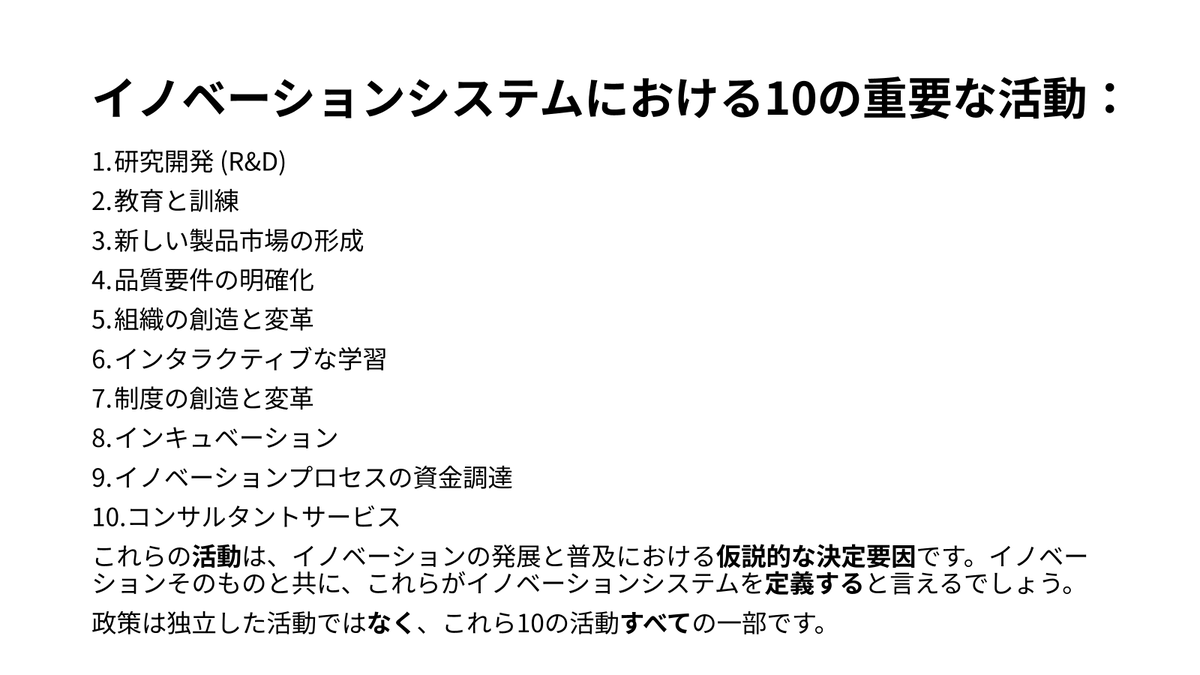
たとえばイノベーションを誘因するときには、公共調達等の需要側(市場形成)の政策も必要になりますが、科学研究から出発する線形モデルで科学技術イノベーション政策を考えてしまうと研究成果の最大化にばかり注目が当たってしまい、中々そうした発想にはなりません。
また、需要側から見てみると(たとえば気候テック領域等)、事業化に必要な科学研究が日本で行われていない、ということがしばしばあります。
そうした場合は需要を元にした科学研究など追加でが行われればイノベーションとなり得ると思いますが、供給モデルや線形モデルをもとに、既存の研究開発を次の市場へと『橋渡し』する形での商用化が研究開発体勢だと、それが受け入れられづらい状況です。
たとえばそうしたアプローチでスタートアップが研究開発をしようとしても、「大学の最新の研究ではないから」と、政府から支援が受けづらい状況が続いています(たとえばNEDOの補助金を取りづらいなど)。
このあたりは以下のスライドなどでも少しお話しています。
ただ、スタートアップを支援する側からすると、市場・需要を元にして、その実現に必要な技術を開発する、というトップダウンのアプローチのほうがイノベーションは起こりやすいのではと感じています。
これは科学研究を否定するものではなく、供給サイドからの研究と需要サイドからの研究が両方必要だろうということです。イノベーションは供給側と需要側からの挟み撃ちで考えていく必要があるのだろうと思います。
「科学技術イノベーション」と、STI を同時に語ろうとすることでこのあたりが混乱しやすいのも課題だろうと思います。
上記の Edquist の PDF で提案されているように、線形モデルではなくシステムアプローチで考えることを明示するか、もしくは同PDFで示唆されている通り、イノベーション政策と科学研究政策は少し分けて考えた方が良いのではと思います。
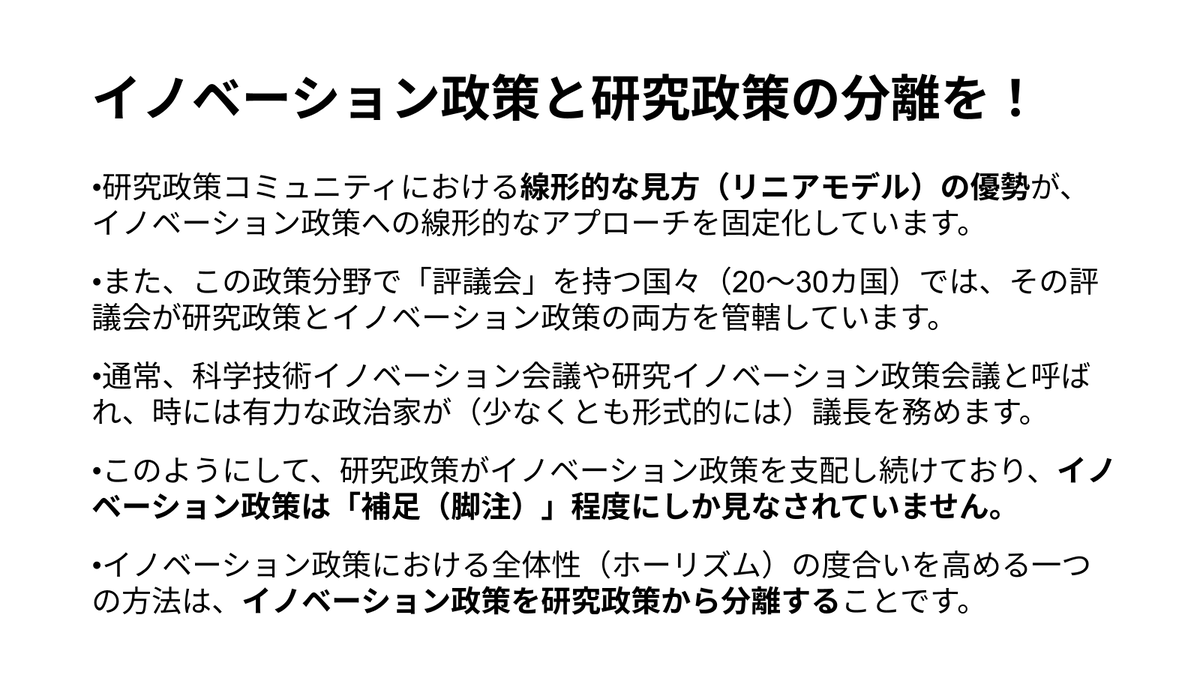
研究政策とイノベーション政策はそれぞれがそれぞれで重要です。経済効果を前提とする「イノベーション」につながらない研究も大事だからです。一方で、イノベーションも大事ですが、必ずしも研究や発明が必要かというとそんなことはありません。Innovation ≠ Invention とはよく言われていることです。
だから、それらを一緒に語ってしまうことで、双方にとって悪い影響が出るのでは、というのが、どちらかというとイノベーションサイドの現場で働く私個人の現時点の感想です。
という趣旨のものを以前アイデアボックスに投稿したのですが、ブログ記事で供養しておきます。